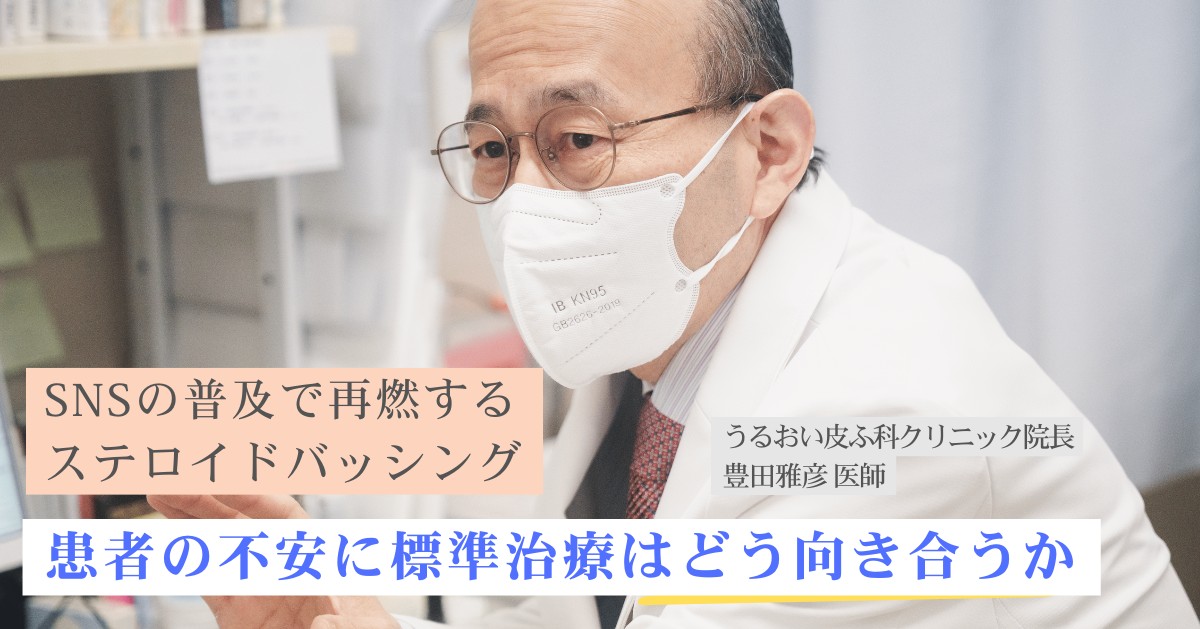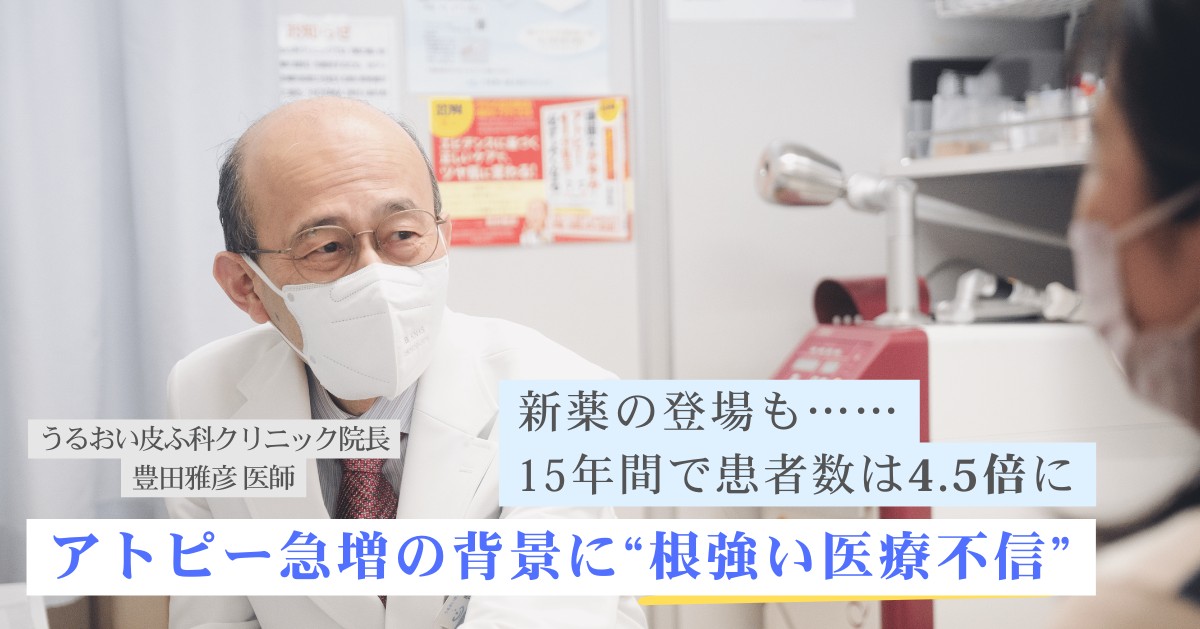「小4からリスカ」…進む自傷行為の低年齢化、学童期からのメンタルケアは急務

画像:LINEオープンチャットの投稿より引用。画像は個人情報保護の観点から一部加工しています。
(取材・文:遠山怜)
小学校高学年の約2割が自傷経験あり
リストカットを含む自傷行為といえば、10代後半の若者が行うことをイメージする人は多い。特に、青年中期(14〜17歳)は進路選択の問題や対人関係の複雑化が起こることから、学校側でも自殺予防教育・心理指導を強化する傾向がある。
一方、自傷行為の支援現場からは「それでは遅い」という声も。
厚生労働省が公表した令和6年度版自殺統計によると、調査開始時の1980年以来、児童・生徒の自殺者数は過去最多を記録した。データによると、前年と比べ、全体の総自殺者数は減少傾向にあり、年代別の自殺率がほぼすべての年代で減少に転じた中で、10代の自殺率は横ばいとなった。
学童期の子どもたちのメンタルヘルスの悪化を裏付ける調査はほかにもある。2020年の調査では、小学生4〜6年生のうち約2割の生徒が、髪の毛を抜く、自分をたたくなど意図的に自分を傷つけたことがあると判明。小学校高学年のうち約2割の生徒が、心理的サポートを必要とする状態下にあると明らかになった。
精神的な発達途上で、早くから情報に触れるリスク
こうした傾向は統計上のデータにとどまらず、実際の支援現場で働く人からも同様の報告が相次いでいる。自傷行為の当事者・支援者に共助の場を提供する、一般社団法人日本自傷リストカット支援協会によると、小学生の子を持つ親からの相談は年々増加傾向にあるという。同協会の発足当初からサポーターとして活動する佐藤さん(仮名)は、こう証言する。
(佐藤)「当協会では当事者のほか、当事者家族からの相談も受け付けています。この数年の間で、自傷している当事者の年齢がどんどん低下していると思います。サポーターをはじめた当初は、高校生ぐらいの年代が多いだろうと想定していましたが、実際には小学生で自傷行為をしているという相談が少なくない」
佐藤さんは普段、地方都市で訪問看護ステーションの看護師として勤務しており、同業間でもそうした事例をよく耳にするという。
「医療従事者の間でも、10〜12歳ぐらいの子どもで自傷行為をしているケースが増えていると問題視されています。親が異変に気づいて病院に連れていく頃には、すでに重度の精神不調が常態化しているかもしれない」
「どんな子が何に悩んでいるのか知りたくて、私はよく10代中心のオープンチャット等を時々見ていますが、小学生で自傷行為をしているという投稿をよく見かけます。特に、生きづらさを抱える学生が集まるチャットでは、小学校高学年でリストカットや市販薬の過剰服薬を繰り返しているという報告が多く、問題の深刻さは大人と遜色ないと思います」

画像:LINEオープンチャットの投稿より引用。画像は個人情報保護の観点から一部加工しています。
彼らが自傷行為を知ったきっかけは、圧倒的にSNSが多いという。しかし、佐藤さん曰く、一過性に、いわゆるファッション感覚で行っているのとは違うという。
「その子のなかに、どうしようもない生きづらさがあるんだと思います。子どもにとって、親や学校での人間関係は絶対的なもので、自分では変えることができない。周囲の大人が助けてくれない限り、子どもはストレスを抱え続けるしかない。それで、ネットで知った情報から、自傷行為で気持ちをコントロールすることを覚えてしまい、習慣化してしまう例が多いのではないでしょうか」
「子どもであればあるほど、自分の気持ちを言葉にするのは難しいと思います。大人のサポートがない限り、自分が今どうしてつらいのか何が起きているのかはおろか、助けを求めることもできない。それに、本人は自傷を隠そうとするので、周囲が問題にすぐに気づけなくなってしまう。水面下で精神状態の悪化が進行する恐れがあります」
低年齢児だからこそのリスク
日本における自傷行為の専門家、精神科医・松本俊彦医師によると、自傷行為は「死にたいぐらいつらい気持ち」を解消するために行われており、自殺を目的とした行為ではないという。しかし、低年齢の子どもに限っては、その境界線は必ずしも明瞭ではない。
精神的な未熟さも手伝って、自傷行為の頻度や程度をコントロールしきれず、周囲との人間関係が早くから悪化したり、かえって死にたい気持ちが高まってしまうリスクがある。一般的に、自傷行為は短期的にはストレスをやわらげ、自殺の回避に役立つ側面というもあるが、低年齢児においてはその回避効果がどこまで続くのか疑問が残る。
子どもの孤立を防げるか
政府は、児童のメンタルヘルスの問題に対し、学校を中心とした心理的ケアを拡充するとしている。しかし、心理面に問題を抱える児童は、しばしば不登校になる傾向がありケアの主体である学校につながれない恐れもある。
対策の鍵となるのは、いかに児童心理の専門家を増やし、早期介入を可能にするサポート体制を用意できるか、学校外で心理ケアができる場所をどれだけ構築できるかにかかっている。大人たちの「まだ早い」は、早々に見直すべき時期に来ている。
「皮膚とこころ」では、そんな心と体の間に焦点を当て、さまざまなテーマを切り口に、医師監修のもとメールマガジン形式でニュースレターを不定期でお届け。当事者へのインタビューや独自取材、調査を通じて、当事者が、自身の悩みについて考え、主体的に医療行為を求める手助けとなるような情報発信を行なっていきます。登録はこちらから。
すでに登録済みの方は こちら